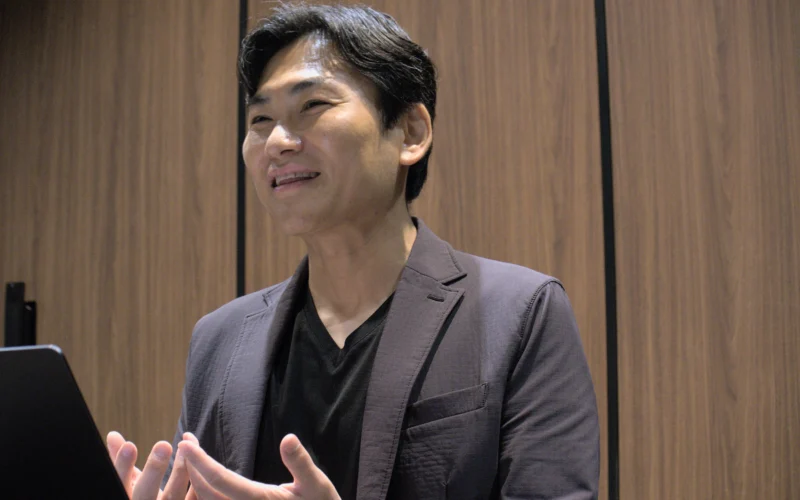【スピーカー】
他力野淳(たりきの・じゅん)
2005年バリューマネジメント株式会社設立、代表取締役に就任。文化財をはじめとした歴史的建造物など地域資源の利活用や観光まちづくりを推進。「施設再生から地域の活性化に繋げ、日本独自の文化を紡ぐ」がテーマ。内閣官房タスクフォース専門員、観光庁専門家、総務省アドバイザーなど歴任。立命館大学客員教授。グローバル起業家団体EO(Entrepreneurs Organization) Japan Region – Regional Chair。
【インタビュアー】
荻原猛(おぎわら・たけし)
株式会社ロケットスター代表取締役社長 CEO。中央大学大学院戦略経営研究科修了。経営修士マーケティング専攻。 大学卒業後、起業するも失敗。しかし起業中にインターネットの魅力に気付き、2000年に株式会社オプトに入社。2006年に広告部門の執行役員に就任。2009年にソウルドアウト株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。2017年7月に東証マザーズ上場、2019年3月に東証一部上場。2022年3月に博報堂DYホールディングスによるTOBにて100%子会社化。博報堂グループにて1年間のPMIを経てソウルドアウト取締役を退任。2023年4月に株式会社ロケットスターを設立し、代表取締役社長 CEOに就任。50歳で3度目の起業となる。
阪神・淡路大震災での被災経験をきっかけに、「地域の価値を守りたい」という想いを抱き、30歳で起業したバリューマネジメント代表取締役・他力野淳さん。
人口減少や文化財の保存・活用といった社会課題に真正面から向き合い、100年を超える歴史的建造物などの運営を手がけ、ひとつひとつの積み重ねと努力の姿勢が、地域からの信頼につながっています。
舞台は、京都から全国へ。
歴史や文化の「保存と運用」という困難な領域に、民間の立場から挑み続けるその歩みには、「地方創生」という言葉だけでは語り尽くせない、本質的な問いと実践が詰まっています。他力野さんの原点や事業の真意を、ロケットスター代表取締役の荻原猛が伺います。
阪神・淡路大震災がもたらした転機
荻原:これまでのキャリアや挑戦の中で、文化資産や地域再生に取り組もうと決めた原点はどこにあったのでしょうか?
他力野:原点は、やはり阪神・淡路大震災の経験です。僕は神戸で育ち、中学校を卒業する頃には、自分で何かを起こそうと考えていましたが、当時は正直、お金儲けが目的でした。
しかし、震災が起きた21歳の時に、自分が何も役に立っていないことに気づいたのです。まちは壊滅し、コミュニティがバラバラになってしまい、大切なものが失われていました。建物は建て直して綺麗なまちになったとしても、愛着のあるまちは戻ってこない。失ってから初めて大事なものに気づく、そのもどかしさを痛感しました。

30歳で起業を決めた時、何をすべきか分からず模索しましたが、人口減少という日本の長期的な課題に向き合う必要があると感じました。人口減少はじわじわと地域や文化を蝕んでいく問題であり、これに対して文化財や地域活性化の分野で価値を創出したいと考えたのが始まりです。
また、ビジネスの構造を見た時に、良いビジネスモデルやお金は世の中に溢れているものの、運用や経営のプロフェッショナルが少ないことに気づきました。優れた文化や施設も、正しいマネジメントがなければ活かせない。そこで「価値をマネジメントする」という意味を込めて「バリューマネジメント」という社名を付けました。
当時は誰も注目していなかった文化財の保存や活用に取り組み始めましたが、人口減少と税収減少が進むなかで、これからの地域の持続には民間の積極的な関与が不可欠だと強く実感しています。
よそ者からはじまった、京都での信頼構築の道のり
荻原:数ある地域の中で、京都という土地を起点に事業を築くことを選んだ理由を教えてください。

(インタビュアー・荻原氏)
他力野:京都のある民間の建物オーナーからの依頼がきっかけでした。100年以上の歴史がある建物を残したいが、自分たちだけでは維持が困難だということで、私たちに声がかかったのです。営業は一切していませんでしたが、お話をいただく形で京都での活動がスタートしました。
当時は新築の再開発が主流で、古い建物を活かしたまちづくりは否定的に見られていました。私たちの取り組みは「建物を生かすまちづくり」という理念のもとで始まりましたが、最初は批判も多く、特に京都では難しい挑戦となりました。
荻原:京都で最初に手がけられたプロジェクトについて教えてください。また、特に印象に残っているターニングポイントは何でしたか?
他力野:最初に手がけたのは、明治3年創業の「鮒鶴(ふなつる)」という屋号の建物です。料理旅館を営んできた、京都でも名の知れた老舗でした。しかし代々受け継がれてきた建物も、時代の流れとともに運営が難しくなり、一度は他の事業者に貸し出されたのですが、結果的には裁判沙汰になるほどのトラブルに発展しました。オーナーが非常に傷ついており、「誰も信用できない」という状態でした。
そんなタイミングで、私たちに声がかかりましたが、最初の空気は完全に「どこの馬の骨が来たんだ」というものでした(笑)。京都における「よそ者」への風当たりは強く、資産家であればあるほど、金目当ての人間ばかりが寄ってくるという不信感を抱えているのです。ですから、私たちが提案したのは、「この建物の歴史を尊重したい」という姿勢でした。

(「鮒鶴」の外観)
通常なら新しい屋号で運営するところを、「『鮒鶴』の名を使わせてほしい」とお願いしました。当然、反対されましたが、「100年以上続いた名前を未来につなぎたい」と譲らず、最終的にはアルファベット表記での使用が認められました。今では漢字表記に戻っていますが、これが信頼構築の第一歩でした。
ただ、そこからが本当の勝負でした。市役所から毎日確認の電話が入り、地域の人からは「よそ者が何をしているんだ」、時には「歩くな」と言われることも。それでも地域のルールを徹底して守り、清掃活動などにも積極的に参加することで、少しずつ信頼を得ていきました。
今では、最も警戒していたオーナーが一番お客さんを紹介してくださる存在になりました。地域の方々からも「任せて大丈夫」と言われるようになり、現在もその施設の運営を続けています。
京都で学んだのは、成果以上に「スタンスと姿勢」が信頼の土台になるということです。すべての取り組みは地域からの相談によって始まっています。自分たちから営業したことは一度もありません。地域の「この建物を残したい」という声が、今の事業の原点になっています。
京都での実践を全国へ
荻原:地域ごとに風土や慣習の違いがある中で、京都で築いた成功モデルは他県でも活かせるのでしょうか?
他力野:京都で培ったこのモデルは、全国でも通用すると考えています。重要なのは、地域の構造に共通点があるということです。
東京・銀座で最初に手がけたのは、伝説のレストラン「伝説のフレンチレストラン」の案件でした。銀座のような都心部であっても、実態は村のような構造を持っている。たとえば、銀座で何か事業を始めようとすると、特定のキーパーソン3人、5人の了承がなければ何も進まない、という世界がある。これは渋谷でも、地方のまちでも同じです。つまり、東京も地方も「村社会」という点では変わらないんです。
地域ごとの価値観や慣習を尊重しながら、彼らが大切にしている領域には踏み込まず、代わりに「その地域で足りていない部分」を見極めて補う。それが私たちの役割です。
私の中では、それをジグソーパズルのようなものだと捉えています。まちという絵を完成させるには、すべてのピースが必要です。ひとつでも欠けていれば絵は完成しません。だからこそ、まずは地域にある課題や空白を丁寧に「見える化」する。そして自社で担える部分は担い、足りない部分は他のプレイヤーと連携して埋めていく。そうして地域全体の絵を完成させていくのです。
-1024x683.webp)
(Destination Management Organization(観光地域づくり法人)との締結式)
地域と共に歩む、現場主義の経営スタイル
荻原:地方で事業を広げていく中で、地域によって感じた難しさや、乗り越え方の工夫があれば教えてください。
他力野:地域に根差した事業を展開していく中で、最も大切なのは「地域との関係性」です。これがすべてだと言っても過言ではありません。成功したときにスポットライトを浴びるのは、私たちではなく、その地域の人であるべきなのです。
たとえば、地域のメディアでは、その土地の人が主役として取り上げられる構図を大切にしています。私たちは黒子として後ろに立ち、エンジンとして機能する。それに対して、全国メディアでは、私たちが前に出て取り上げられることもあります。そこでは、地域での活躍を積み重ねるようなかたちで私たちの存在が見えてくる。つまり、誰が表に立つかはメディアの性質や目的に応じて設計する必要があるということです。
荻原:地域ごとに異なる風土や慣習がある中で、人材の配置や事業運営にはどのような工夫をされているのでしょうか?
他力野:地域で活動する中でよく誤解されがちなのが「土着でなければならない」という考えです。確かに地元出身者が地域に入る意義はありますが、それだけでは成り立ちません。私たちは全国採用を行い、各地に人材を送り込んでいます。社員は住民票を移して現地に暮らし、拠点の登記や納税も行いながら地域に溶け込んでいきます。
その一方で、地元雇用も積極的に進め、時間をかけて人材を育てています。結果的に、地元採用の比率は年々高まっていますので、全国採用スタッフが地域に定住するケースと合わせて両輪で進めています。
「地方で働きたい」と願う若者は多い一方で、キャリアの受け皿が不足しているのが現状です。私たちは、そうした想いを受け止める存在でありたいと考えています。新卒採用でも多くの応募が集まっているのは、地方への関心や期待の表れだと思います。

(各地方でスタッフが活躍)
荻原:御社の事業モデルや強み、他社と比べたときの独自性はどこにあると考えていますか?
他力野:私たちが扱うのは主に地域資源、つまり歴史的建造物や自然といった地域の宝物です。世の中の多くの会社は「リノベーション」という手法で古い建物の内部を大胆にデザインし直し、現代に映える形に変えることで収益を上げています。しかし、地域の文化財を勝手に作り替えることは、地元の方々にとっては抵抗感や反感を生むこともあります。
その点、私たちは「保存」を第一に考え、文化庁や自治体、地域の意向を尊重しながら、本来の姿をできるだけ守ることに努めています。だからこそ、地域と対立することがほとんどありません。
保存と運用の両立は難易度が高い領域ですが、それに特化してきた私たちだからこそ、「保存したい」ときに声がかかります。重要文化財をはじめとした建物を、宿泊施設として管理・運営できるのも、そうした実績の積み重ねがあってこそ。他社にはない独自性であり、私たちの最大の強みです。
荻原:事業を続ける中で、「この瞬間が一番嬉しい」と感じるのはどんな時でしょうか?具体的なエピソードがあれば伺いたいです。
他力野:本当に求められている、という実感が強くあります。地元のオーナーさんや地域の方々が心から喜んでくれる姿を見ると、それが従業員の大きな励みとなっています。みんながその思いを感じ取り、一緒に向き合いながら事業を進めていく過程は、とてもやりがいがあります。
ビジネスというとどうしてもお金や利害関係が絡みがちですが、私たちの取り組みはそういった枠を超えています。利益が直接入らない地域の人たちが応援してくれることに本当に感謝していますし、それが何よりの原動力です。

(伊賀市事業のステークホルダーの皆さま)
荻原:地方創生における政治と経済の関係についてどうお考えですか?
他力野:社会は本来、政・官・民の三者で成り立ち、それぞれが役割を担っています。理想的な構造ですが、選挙制度などの現実的な課題から、政治だけでは解決できないことも多いと感じています。
私の家系も地方の庄屋を務めていましたが、地域課題の本質が政治で解決されにくい現状を見て、経済を通じてアプローチする道を選びました。地域間の格差や東京一極集中は、日本全体にとってリスクです。歴史ある土地を守りながら、それぞれの地域が役割を持ち、支え合うことが重要だと考えています。
私が京都に拠点を置いたのも、よそ者が時間をかけて受け入れられてきた土地だから。京都の文脈を理解しつつ、全国に点在する地域資源を活かす取り組みを、これからも事業を通じて続けていきたいと思っています。
未来の地方創生に向けたメッセージ
荻原:これから地域を舞台に挑戦を始める次世代の経営者に、どんなアドバイスやメッセージを届けたいですか?
他力野:今の社会では東京一極集中が進み、「東京にいなければ儲からない」と考える人も多いですが、地方でも本気で挑戦している事業者は数多くいます。ただし、想いや理想だけではなく、それを実現する「力」と「戦略」が必要です。
私たちは都心に拠点を置きつつ、地方にも拠点を持ち、双方を結びつけることで経済を循環させています。地方が分断されていては気づかない課題も、都市との接点があれば解決の糸口が見えます。双方に拠点があるからこそ、流れを循環させ、地方に経済を還元できると考えています。
オンライン化が進む時代でも、リアルな拠点を持ち、人と人が直接つながる場所をつくることが重要です。そうした場を基盤にすれば、地方発で百億円規模の事業を生み出すことも可能です。
地方を本気で勝たせるには、小さくまとまるのではなく、「どう勝つか」を戦略的に設計すること。これからは、その設計力がますます求められていくと思います。

「地域の価値を守りたい」と志を立て起業をした他力野さんの歩みは決して派手ではなく、信頼を1つずつ積み重ねてきた歴史でした。京都での苦闘、地域との対話、文化財を守りながら経営を成立させる挑戦は、単なる地方創生という言葉を超えて、日本の未来に問いを投げかけています。利害や収益の枠を越え、地域の人々が笑顔になる瞬間を原動力とする姿勢は、多くの経営者に参考となるでしょう。本稿が、地域とともに歩むビジネスの可能性を考える一助となれば幸いです。
(クロスメディアグループ株式会社 代表取締役 小早川幸一郎)

【企画・制作】
クロスメディアグループ株式会社
ビジネス書の出版を中心に、経営者や企業のブランド価値を高める編集を手がける総合コンテンツ企業。取材を通じて経営理念や魅力を言語化し、書籍、Web、映像など多様なメディアで発信。(広報室:濱中悠花)