多田匠(ただ・たくみ)
株式会社天盃 五代目専務取締役。1994年5月1日生まれ。酒蔵が遊び場という環境の中で育つ。高校卒業まで地元・福岡で過ごした後、大学進学を機に上京。上智大学に入学し、社会学および社会福祉を専攻。大学卒業後はオプトグループ(当時)のソウルドアウト社に入社し、インサイドセールス、広告運用コンサルティング、企画設計、戦略プランニングの4領域に従事。ビジネスの現場でマーケティングの実務経験を積む。2021年5月1日、株式会社天盃に加わり、五代目専務取締役として新たなスタートを切る。伝統を守りながらも新たな挑戦を続け、地元福岡から世界に向けたブランドづくりに取り組んでいる。
大手メーカーの存在感が大きく、若者離れが進む焼酎市場。依然として「モノ消費」の風潮が根強く、逆風が吹く業界の中で、福岡の老舗焼酎蔵「天盃」は、「蒸溜酒の文化を次世代につなぐ」という使命を掲げ、独自の道を歩んでいます。
「守るべきは形式的な伝統ではなく哲学や理論」と強調する五代目多田 匠氏。焼酎づくりに向き合い、革新を続けることで文化を未来へつなぐ、その挑戦について語ります。
世界を見据えた独自の焼酎づくり

日本の酒類市場には、大手焼酎メーカーが数多く存在しており、手に取りやすい価格の商品を広く届けています。そのなかで私たち天盃は、量ではなく、価値を重ねるものづくりを志しています。限られた生産規模だからこそ、一滴一滴に想いを込めた、独自の蒸溜酒を生み出しています。
天盃を大きな木と例えるなら、土壌は「蒸溜酒の文化を次世代につなぐ」という使命です。蔵元としてのすべての意思決定の基準は、この使命になっています。
また、その土壌に根を張るのが「世界に誇れる蒸溜酒づくり」という哲学です。蒸溜酒の文化を次世代につなぐためには、焼酎の価値を高めて、世界に誇れるものにしなければなりません。天盃は、それにふさわしくない部分をすべてなくし、理念と哲学に裏付けされた文化的な価値を持つ焼酎づくりを行っています。
三代目である祖父は、焼酎が「安く酔うための酒」という立ち位置だった時代に、独自の蒸溜機および蒸溜技術の確立、地元の福岡と佐賀の大麦だけを100%使い、当時一般的に使用されていたイオン交換樹脂・炭素濾過・薬品加工等を一切排除した無添加な本格麦焼酎を開発しました。代替わりした父は、祖父から引き継いだ焼酎を基盤に、香りと味の部分、いわゆる「酒質(お酒のクオリティ)」を飛躍的にアップデートさせました。
そして、木の幹部分は「大麦の本当の旨さを引き出す」という理念です。天盃の焼酎は商品によって、それぞれ異なる味わいや香りを持っています。すべての焼酎を作る上で共通しているのは、大麦のポテンシャルを引き出すこと。原料である大麦が持つ甘さとコクを、焼酎で表現します。
その幹に生える枝は、「食卓に幸せを届ける新しい蒸溜酒体験」といった商品のコンセプトです。それに基づいて提供する商品が、枝の先を茂らせる花や葉にあたります。例えば、料理とのペアリングをテーマにした「クラフトマン多田」というブランドや我々が造る焼酎をベースに、コーヒーや黒胡椒などの副材料を使った新しいスピリッツです。
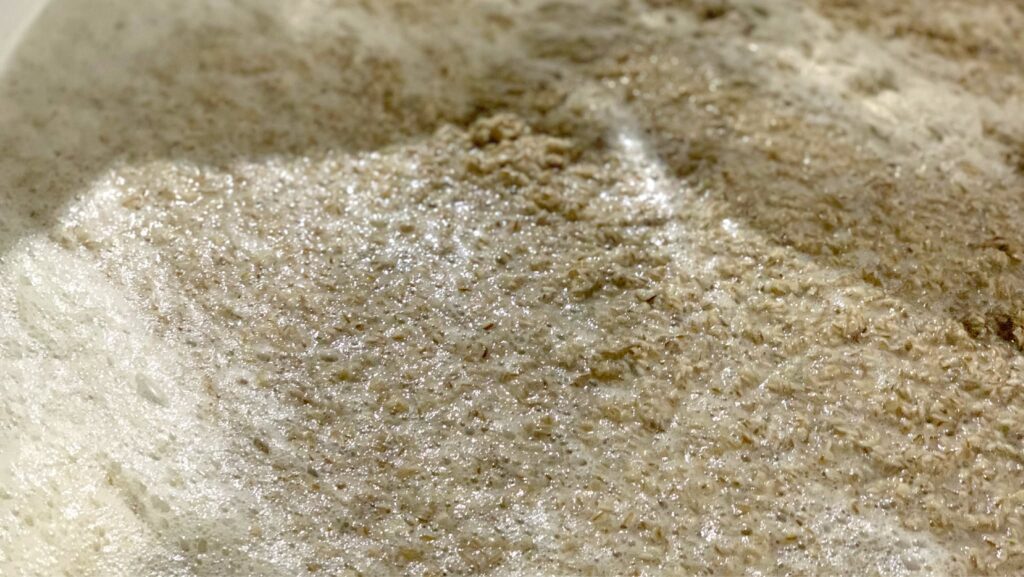
「モノ消費」から「コト消費」へ
近年「若者のお酒離れ」が叫ばれ、焼酎を飲む若者は減少しています。さらに、アフターコロナでライフスタイルが多様化し、可処分所得の使い道が、飲酒以外の娯楽にも向くようになりました。
他の業界では「コト消費」という体験やストーリーに価値を見出す考え方が主流となってきています。しかし、酒類業界ではまだ浸透が進んでおらず、依然として商品のスペック、つまり「モノ」自体の説明に終始しがちです。
例えば日本酒であれば、「純米大吟醸 〇〇絞り」といった情報がラベルに並び、焼酎においても、芋・麦・米といった原料の違いや麹菌・仕込み方法、熟成年数などが訴求ポイントとなることが多い。かつて需要が供給を上回っていた時代は、少ない言葉でも商品自体の価値や魅力は伝わっていましたが、供給過多となった現在、お客様には響きにくくなっています。
こうした状況で「お客様が本当に求めている価値は何か?」と突き詰めた結果、たどり着いたのが、クラフトマン多田における「ペアリング」というコンセプトです。
私たちが考える「クラフト」とは、単なるモノづくりではありません。「作り手の顔が見えるか」「作り手の想いや思想、哲学が込められているか」が重要だと考えます。どのような人が、どんな思想・哲学でつくったのか。そのストーリーをコンテンツとして持ち、お客様にしっかりと伝わっていくことを「クラフト」と定義しています。
「クラフトマン多田」は、料理の味を引き立たせ、食事のシーンを豊かにします。ワインや日本酒では一般的な「ペアリング」ですが、焼酎においては馴染みがありませんでした。焼酎の蔵元である私たちがこの価値を伝えていかないと、お酒を飲むこと以上に魅力的な選択肢がある中で、お客様に焼酎を手に取っていただくことは難しくなります。
もちろん、「美味しいものをこだわって作ること」は重要です。もはや当たり前のことになっていると思います。しかし、品質の良いものが溢れている現代において、それだけでお客様に選んでいただくことは難しい。お客様側の視点に立って、より焼酎を楽しんでいただけるように、付加価値を提供する必要があります。
結果として、良い意味でお客様の中にある麦焼酎のイメージを壊せていると感じています。現在、当社が開発する新しい焼酎は多くの若い方に楽しんでいただいています。30代から40代がお客様のボリュームゾーンになっており、次の世代に着実に蒸溜酒の体験を届けられているのではないでしょうか。

自らの価値を高めることが、地域への最大の貢献になる
先ほど触れた「世界に誇れる蒸溜酒づくり」とは、単に良質な焼酎をつくれば良いわけではありません。たとえ、味わいや香りを引き出すことができても、その過程で地球を汚してしまうようでは、世界に誇れるものとは言えないでしょう。
私たちは、持続可能な焼酎づくりに早い段階から取り組んでいます。例えば、天盃で製造している麦焼酎は、地元の福岡と佐賀の2県にまたがる九州最大の平野「筑紫平野(つくしへいや)」の大麦だけで行っています。
また、焼酎を作る過程で「焼酎粕」という副産物が発生します。一般的には産業廃棄物として処理されたり、メタン発酵による発電に利用されたりもしますが、天盃では、ここ60年程は地元の酪農家の方々に提供し、乳牛の配合飼料として利用していただいています。そして、牛の糞や尿が堆肥となり、最終的には地元の畑へと還元されるのです。地域の資源と地元の人材を活用し、地域内で完結する循環型の仕組みを、早くから手がけていました。
とはいえ、私たちは「地域のために何かをする」ことを別立てで目標にしているわけではありません。私たちが最も強みとする「焼酎づくり」という仕事に真摯に向き合い、その価値を高め続けることこそが、自らの存在意義を磨き上げることであり、ひいては地域の価値をも押し上げていくものだと考えています。
目の前の事業に誠実に取り組み、その文化と営みを次の世代へと確実に受け継いでいく。私たちにとって、それこそが地域への最大の貢献であり、筑前町というこの土地の未来を拓き、より多くの人々に知っていただく道だと信じています。

蒸溜酒の文化を次世代に繋ぐために
天盃の今後のビジョンは2つあります。一つは「焼酎が持つ可能性を深掘り、お客様に届けること」と、もう一つは「さらに次の世代を見据えた未来への種まき」です。
焼酎のペアリングなどソフト面での体験価値や「想いへの共感」「作り手の顔が見える」といったクラフトならではの魅力は、まだまだ伝えられる余白があると思っています。だからこそ、食へのこだわりや熱意を持つ全国の飲食店様へ、私たちの焼酎とその価値を届けていきたいと考えています。
おかげさまで、クラフトマン多田の売上は年々伸びており、ブランドとして着実に成長しています。ANA国際線のファーストクラスの機内食ドリンクメニューや星付きレストランでも採用されるようになりました。私が蔵に加わってから、志を共にする特約店様とのつながりが深まり、結果として約2倍の広がりを見せています。さらに、グローバルな展開も加速させており、今年から新たに取引が始まる国も含め、現在13カ国へ輸出しています。
将来的には、クラフトマン多田のアンバサダーの役割を持つレストランを、まずは、全国に20店舗作りたいと思っています。飲食店様との連携を密にし、お客様との接点を増やすことで、最終的には、より豊かな食の時間を提供できることにつながるでしょう。しかし、これまでの取り組みは、主にお酒を飲む人たちに向けたコンテンツの話が中心でした。一方で、若年層を中心に、そもそもお酒を飲む人が減少している事実があります。
これからは、お酒を飲む人にお酒を提供するという発想から離れる必要がある。お酒を飲む・飲まないにかかわらず、人々が集まる居心地の良い空間にお酒があることで、より豊かな時間や空間を提供できるかもしれません。
次世代の価値観やお金の使い方、お酒に対するイメージの変化を踏まえ、私たち自身も立ち位置を柔軟に変えていくことが必要です。この領域はまだ取り組んでいる最中ですが、酒類業界にとどまらず多くの方と対話を重ねる中で、着実に歩みを進めています。

前進し続けた結果が「伝統」になる
10年後、20年後、さらに次の世代へと、どのようにバトンをつないでいくのか。私たちは、日々の実務を見直し、新しい挑戦を重ね、これまでの歩みを再定義しながら、さまざまな取り組みを続けています。
商売の観点では、すぐに結果にはつながらないことも少なくありません。それでも挑戦を続けるのは、未来が失われるかもしれないという危機感、そして自分自身が後悔したくないという、純粋な「想い」からです。長年受け継がれてきた歴史を絶やすわけにはいきません。家族や天盃で働いて頂いている従業員さんを守る責任もあります。この文化と営みを、確実に次世代へ受け継いでいかなければならないんです。
だからこそ、私たちは前進し続けなければならないと感じています。歴史のある蔵や家業では伝統が重んじられますが、それは今ある文化と営みが続いてこそ意味を持つものです。しかし、その「伝統」に固執し未来を閉ざすのであれば、変化していくことこそが正解だと考えます。

「伝統」は、あくまで結果論に過ぎません。100年間変わらぬ製法も、さらに100年後に支持され続けてこそ、その価値が証明されるのです。守るべきは、形式ではなく、営みの中に息づく「哲学」や「理念」。すなわち私たちが信じる価値観です。
振り返れば、この数年でも多くの挑戦を重ねてきました。これらは伝統を意識して生まれたものではありません。お客様の笑顔を思い浮かべ、より美味しい味わいを追い求めた結果、既存の手法では限界があり、新たな工夫を重ねただけです。それがたまたま日本で誰も手掛けていないことだった。これらもまた結果論に過ぎません。
ですから、神棚に飾られたような過去を守るだけではなく、哲学と理念を胸に絶えず革新を続けるべきだと考えています。その積み重ねが、振り返った時に「伝統」と呼ばれるものになるはずです。
今、私は自らハンドルを握り、未来へ向かってアクセルを踏み込んでいます。時には速度を落とすことや振り返ることもあります。それでも、自らの判断で信じる道を進み続ける。その先に、私たちが目指す未来が待っていると信じています。
編集・取材・文:鬮目 真伸(クロスメディア・パブリッシング)












