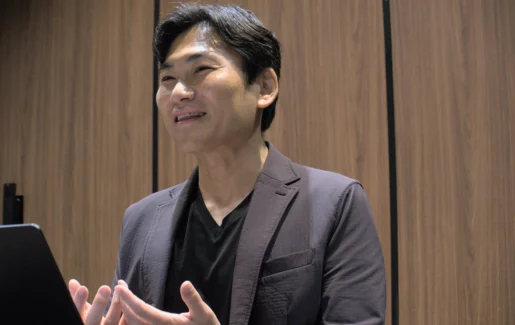【スピーカー】
田中仁(たなか・ひとし)
群馬県前橋市出身。 株式会社ジンズホールディングス代表取締役CEO、一般財団法人田中仁財団代表理事。1988年有限会社ジェイアイエヌ(現:株式会社ジンズホールディングス)を設立し、2001年アイウエア事業「JINS」を開始。2013年東京証券取引所第一部に上場(2022年4月から東京証券取引所プライム市場)。2014年群馬県の地域活性化支援のため「田中仁財団」を設立し、起業家支援プロジェクト「群馬イノベーションアワード」「群馬イノベーションスクール」を開始。2020年には廃旅館を再生して「白井屋ホテル」を開業し、衰退していた地方都市・前橋のまちづくりに奮闘している。
【インタビューアー】
荻原猛(おぎわら・たけし)
株式会社ロケットスター代表取締役社長 CEO。中央大学大学院戦略経営研究科修了。経営修士マーケティング専攻。 大学卒業後、起業するも失敗。しかし起業中にインターネットの魅力に気付き、2000年に株式会社オプトに入社。2006年に広告部門の執行役員に就任。2009年にソウルドアウト株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。2017年7月に東証マザーズ上場、2019年3月に東証一部上場。2022年3月に博報堂DYホールディングスによるTOBにて100%子会社化。博報堂グループにて1年間のPMIを経てソウルドアウト取締役を退任。2023年4月に株式会社ロケットスターを設立し、代表取締役社長 CEOに就任。50歳で3度目の起業となる。

左:荻原猛(おぎわら・たけし)右:田中仁(たなか・ひとし)
地方の再生なくして、日本全体の持続的な成長はありえない。
そう信じて、群馬県前橋市でまちづくりと起業家支援に挑み続けているのが、(株)ジンズホールディングス代表取締役CEO 田中仁さんです。
地方は可能性に満ちている。だからこそ、都市に集中したリソースや視線を分散させ、地域から新たな価値を生み出す必要がある。
田中さんの想いは、ビジネスの枠を超えて、都市と地方の関係性を問い直します。
経営者としてアイウエアブランド「JINS」を一代で日本を代表する企業へと成長させてきたキャリアのなかで、なぜ地方創生にここまで深く関わるようになったのか。そして彼が描く「地方がめぶく」とは、どのような未来なのか。
田中さんの思想と実戦について、ローカルグロース・コンソーシアムの発起人であり、(株)ロケットスター代表取締役の荻原猛が伺います。
民間主導の地域再生プロジェクト
荻原:「ローカルグロース・コンソーシアム」は、地方企業の挑戦を応援したいという思いから始まりました。一方で、すでに全国区で活躍している企業が地域に貢献しているケースも見逃せません。その代表格が田中さんだと思っています。たとえば、廃業していた老舗旅館を買い取り、国内外のクリエイターと一緒に新しい場所として生まれ変わらせた白井屋ホテルの再生は、その象徴的な取り組みですよね。また、2013年からは群馬イノベーションアワードを立ち上げて、起業家の発掘や育成にも取り組まれていて、本当にいろんな角度から地域を動かしてこられていますよね。
田中:本当にありがたいことに、群馬県前橋市での私たちの取り組みは、国や行政機関からも注目されるようになってきました。先日、前橋を訪問された石破総理大臣を私がご案内するという貴重な機会をいただきました。

(前橋市で石破総理大臣をご案内)
午前中にJINSの複合施設「JINS PARK」を、午後はまちなか商店街をご案内させていただき、その様子は全国ニュースでも取り上げられました。今、全国を見ても民間主導で街を動かしているケースが少ないからでしょうね。
荻原:今の日本は、東京一極集中の流れが続いています。そんな中で、なぜあえて地方に軸足を移し、投資や事業展開を進められたのでしょうか?
田中:2011年にモナコで開催された、起業家の世界大会への参加が転機となりました。各国を代表する起業家たちが一堂に集まり、自らのビジネスと社会貢献を語る華やかな場。そこで、世界の起業家の多くが、個人の資産や時間を使って社会貢献している姿を目の当たりにし、衝撃を受けたんです。孤児を支援している人、震災被害地域に多額の寄付をしている人。利益だけでなく社会的意義を追求する姿勢が、世界の起業家の“当たり前”でした。
一方、当時の私は、会社を大きくして雇用を増やすことが社会貢献だと信じていました。もちろんそれも一つの手段ですが、欧米の起業家たちが個人のお金を使ってまで社会と関わっている姿を見て、「自分ももっと有意義なお金の使い方があるのではないか」と考えるようになったんです。贅沢を否定するわけではありませんが、それ以上に、誰かのためにお金を使うことの価値を強く感じました。
荻原:世界の起業家たちから刺激を受けたのですね。ご自身の中で、具体的にどんな変化が起きたのでしょうか?
田中:当時の日本は、東日本大震災の直後ということもあって、社会や地域との関係性が改めて問われていました。私も次第に「自社のためだけに力を注ぎ続けていていいのか」と思うようになりました。同時に、50歳という節目に、これまで社会から得てきた恩恵を何かの形で還元したいという思いも芽生えていったのです。
そこで注目したのが地方です。東京は情報も人材も資本も集まる都市ですが、消費中心の構造。実際に生産や供給を担っている地方こそが、国の成長を支える要ではないかと思ったのです。その地方が人口減少や経済衰退によって弱ったままであれば、日本の持続的な成長はないということを強く感じました。
私の出身地である前橋も、中心街の空洞化が進むなど、「元気のない地域」になっていました。ここにこそ地域を活性化させるプレーヤーが必要だと感じ、起業家の育成やまちづくりへの関心が高まっていきました。
そこで、2013年には「群馬イノベーションアワード」を立ち上げ、本格的に地域の再生に関わるようになりました。2014年には起業家教育のスクールも始め、地域の若者たちがチャレンジできる環境づくりを進めました。東京から企業や人材を前橋に引き寄せる動きも加速しており、「地方から日本を変える」挑戦を続けています。

民が動き、官が支える。理想の地域活性モデル
荻原:地方に拠点を構えることで、JINSの事業や経営にどのような成長機会や可能性が生まれていますか?
田中:当初、前橋での「まちづくり」の取り組みは、JINSとは無関係の個人的な活動でした。会社の名前は出さずに取り組んでいましたが、誠実に続けていると新たなネットワークが生まれました。「この町を良くしたい」という真っ直ぐな姿勢に多くの方が共鳴してくださったんだと思います。こうした利益を目的としない社会との関わりは、SDGsやESGが注目され始めた近年、会社としても重視されるようになってきています。
荻原:田中さんご自身が、なぜそこまで地域のことに力を注ごうと思われたのか、もう少しお聞かせいただけますか?
田中:そもそも人間って、生まれ持って“誰かの役に立ちたい”という気持ちを持っていると思うんです。もちろん、欲もあるけれど、それだけではない。そういう利他的な思いを発露させられる環境が、これまでの日本社会にはなかなかなかった。でも、まちづくりには、その気持ちを呼び起こす力があるんです。
実際、私が前橋で動き出したことに刺激を受けて、地方への貢献意欲をもつ仲間が増えています。分かりやすい例をあげると、NewsPicks前社長・坂本大介さんは地元・愛媛に拠点を移して地域活動に注力していますし、ビズリーチの創業者・南壮一郎さんも山梨で農業に関わる活動を始めています。
ホテルをつくる人もいれば、カフェを開く人もいる。ロールモデルがあることで、それぞれが自分にできることを想像しやすくなり、起業家としての生き方が広がっていくんです。
荻原:そもそも田中さんにとって「地方創生」とはどういう状態を指すものなのでしょうか? また「地方が活性化する」姿をどうイメージされていますか?
田中:私が理想とするのは、「民主導・官サポート」の仕組みです。つまり、地域内の民間人が主役となって自らの意思とアイデアで動き、行政はそれを支援する役割に徹する。そんな関係性です。
今の日本では、民間主導の地方活性化がまだまだ不足しています。国がいくら資金を投入しても、当事者たちの覚悟と自走力がなければ、持続可能な発展にはつながりません。
大切なのは、現場を知る民間が責任を持ってプロジェクトを推進すること。行政がそれを後押ししてこそ、地方創生はうまく機能するように思っています。

続けて、かたちにして、得られる信頼
荻原:地方展開を進めるうえで、地域の人をどのように巻き込み、理解と共感を得てこられたのでしょうか?
田中:最初は「民間にまちづくりなんてできるわけがない」と行政の幹部は否定的でした。
地域では、発言権を持っている方がある程度決まってしまっていて、それ以外の“目立つ人”や“自己主張する人”に対して慎重なんです。そこで私が大切にしていたのは、「覚悟の質と量」をもって本気度を示すということです。それを続けることで、少しずつ信頼が積み重なっていきました。
たとえば、かつて名門旅館だった「白井屋ホテル」。2008年に廃業した建物を私が買い取り、ホテルとして再生しました。最初は「できるわけがない」と言われていましたが、建物が完成して初めて、「本気なんだな」と認識してもらえたんです。耳で聞く話より、目で見える実績こそが人の信頼を動かすと、改めて実感しました。
荻原:信頼を積み重ねていく中で、地域の人たちと“仲間”になっていくために、具体的にどのような工夫をされてきたのでしょうか?
田中:私が意識しているのは、自分だけが資金を出すのではなく、地域の人々と共に身銭を切る仕組みをつくることです。誰かに“支援する・される”という関係ではなく、同じ立場でリスクをとる仲間になる。そうした構造が、まちを共に動かす真の土台になると信じています。
地元の“名もなき仲間”とコミュニティーをつくりながら少しずつ実績を積んでいくと、当初は懐疑的だった社内の空気も変わっていきました。会社に注目が集まり、他の自治体の首長や著名人が視察に訪れるようになったことで、社員たちも「もしかして社長、良いことをやっているのかも」と思ってくれたのではないでしょうか(笑)。
今では官民連携のプロジェクトも実現し、国や行政と協働する取り組みも進んでいます。けれどそれも最初から用意されていたわけではなく、自ら動き、地域とともに結果を出してきたからこそ得られた信頼の証だと思っています。
結局のところ、共感というのは最初から得られるものではなく、やり続けて、見せて、かたちにする中で、じわじわと生まれてくるものなんですよね。
アートが放つ、街と人の視点を変える力
荻原:JINS PARK内で、アートの要素を取り入れた「アート体験プログラム」を導入された背景と思いを教えてください。
田中:アートは「正解のないもの」です。ビジネスの世界では常に論理や成果が求められますが、“よくわからないもの”と向き合う時間こそが、創造性や感受性を育んでくれる。そこにアートの価値を感じています。

(JINS PARK 前橋)
実は、もともとアートには全然興味がなかったのです(笑)。でも、当社の顧問をしていた元エルメスのアート責任者だった方とともに、海外の美術館を訪れるうちに「面白いかもしれない」と感じるようになったのです。自然とアートへの関心が芽生えていきました。
白井屋ホテルでは、建築家・藤本壮介さんの世界観の中にアートを組み込み、建物そのものがアート体験になるように設計されています。前橋のホテルにいながら世界レベルの創造性に触れられる場所として機能しています。

(白井屋ホテル 外観 Green Tower ©Ben Richards)
群馬のような地方都市においても、アートや建築の力で街の空気を変えることはできます。実際、石破さんが視察に来られたり、全国から人が訪れたりするようになったことで、地元の方々のアートを見る目も変わったように思います。
今では企業活動にも積極的にアートを取り入れ、社員が日常的にアートに触れられるようにしています。すぐに仕事に直結するわけではないけれど、なにかの拍子に“ふとした気づき”や“ものの見方の変化”を生む可能性がある。そんな余白や刺激のある環境を、企業として用意しておくことはすごく大切だと感じています。

(JINS本社オフィスの一角)
「モデルなき挑戦」だからこそ価値がある
荻原:国内外問わず、企業経営や地域づくりをする上で、ロールモデルにしている都市や企業はありますか? もしあれば、その理由もあわせてお聞かせください。
田中:尊敬する企業や素晴らしい都市は数多くあります。しかし、現在のまちづくりにおいて特定のロールモデルを持っている訳ではありません。前橋での取り組みは、どこかの都市や企業を模倣したものではなく、自分たちの手でゼロから形にしてきました。

(JINS PARK前橋)
たとえば今、前橋駅から群馬県庁までの約1.5kmを、電動自動運転バスが走る“公園化された道路”にするという前例のないプロジェクトが進んでいます。もともとは国道や県道だった道路を公共交通と歩行者中心の公園のような場所にして、都市の真ん中に新たな人の流れと景観を生み出す構想です。群馬県・前橋市・国土交通省が連携して取り組んでいます。こんな都市改造を地方都市で実現しようとしているのは、まさに“ロールモデルなき挑戦”だと思います。
荻原:田中さんが思い描く「前橋の理想の未来像」とは、どのようなものでしょうか?
田中:「めぶく街」、それが私の理想とする前橋の姿です。市民一人ひとり、あるいはこの街を訪れた人たちが、自らの可能性に気づき、何かを始めるきっかけを得られ、成長できる街。注目を集めるだけでなく、内側から活力があふれるような場所にしていきたいです。

荻原:地方発で成長を目指す若手経営者や次世代リーダーたちへ、メッセージをお願いします。
田中:「どうせやるなら本気で」「覚悟の質と量が結果を分ける」。これらは私が大切にしてきたことです。
多くの人は、無意識に自分で限界を決めてしまっています。でも、集中し、継続すれば、可能性は必ずひらけます。実際、かつてシャッター通りだった前橋が、いまや日本で最も注目される街になっているんです。私自身も信用金庫職員からスタートし、ビジネスに挑戦したことで今があります。さらに地方都市を変える挑戦にも関わることができています。
大切なのは、能力ではなく「パッション」。それこそが何かを成し遂げるために必要な原動力です。だからこそ、ぜひ何事にも夢中になって挑戦してみてください。
田中さんの前橋市での取り組みは、単なる地方再生ではなく、一人ひとりの挑戦心に火をつける壮大な実験だと感じました。覚悟の質と量を示し続け、目に見える実績で共感を生み続ける田中さんの行動はまた、経営者としての社会的役割を私たち後輩へのメッセージのようにも思いました。
(クロスメディアグループ株式会社 代表取締役 小早川幸一郎)

【企画・制作】
クロスメディアグループ株式会社
ビジネス書の出版を中心に、経営者や企業のブランド価値を高める編集を手がける総合コンテンツ企業。取材を通じて経営理念や魅力を言語化し、書籍、Web、映像など多様なメディアで発信。(広報室:濱中悠花)